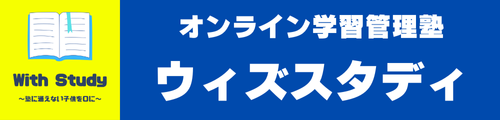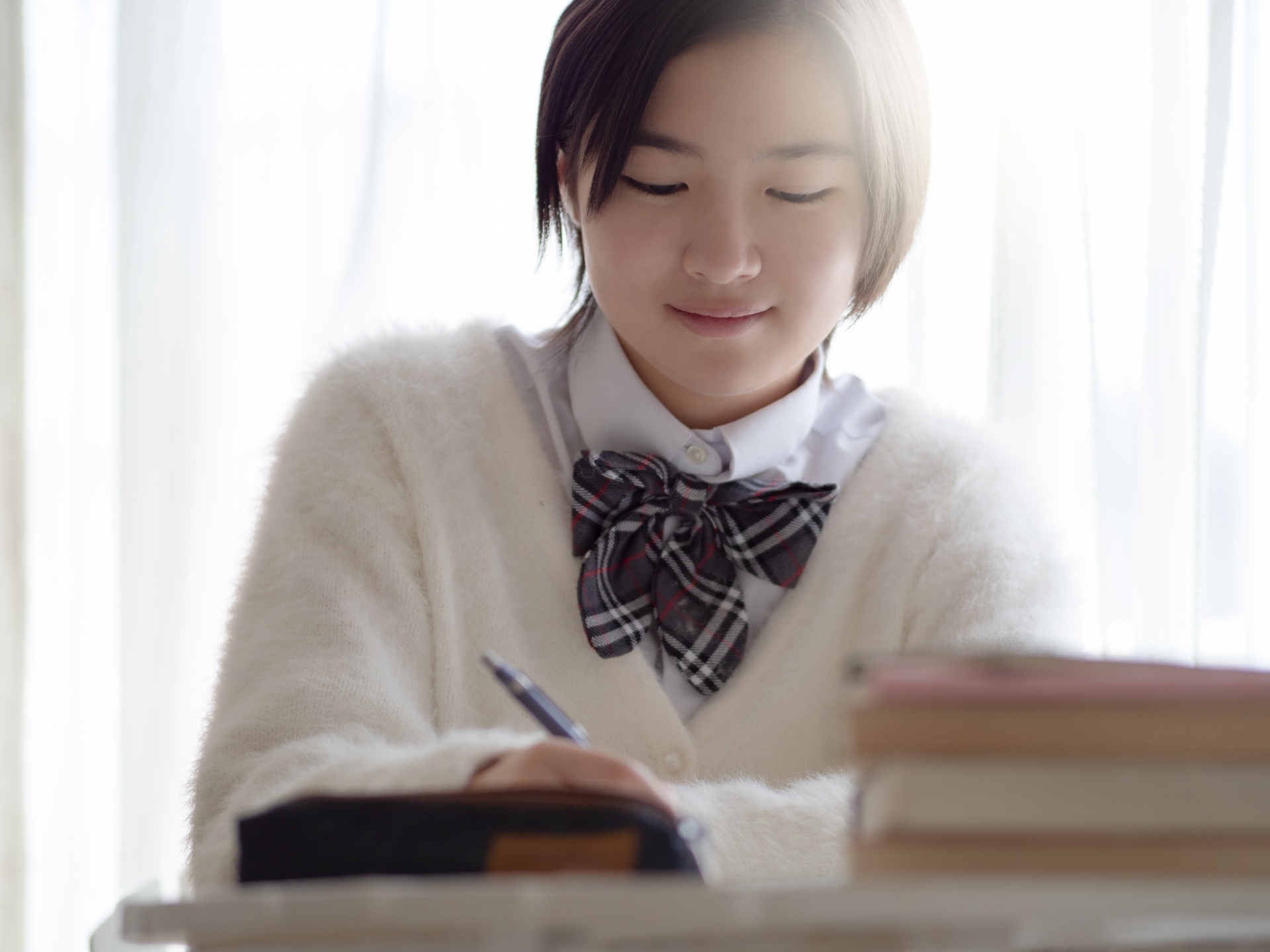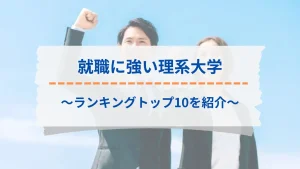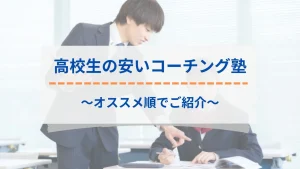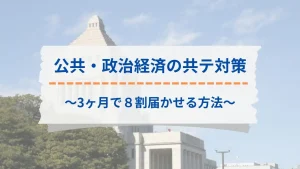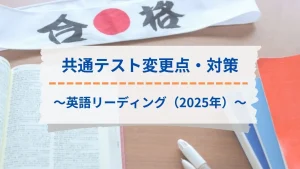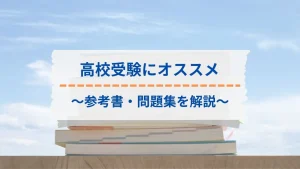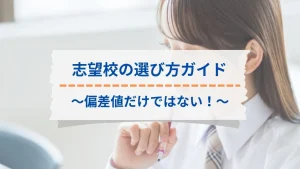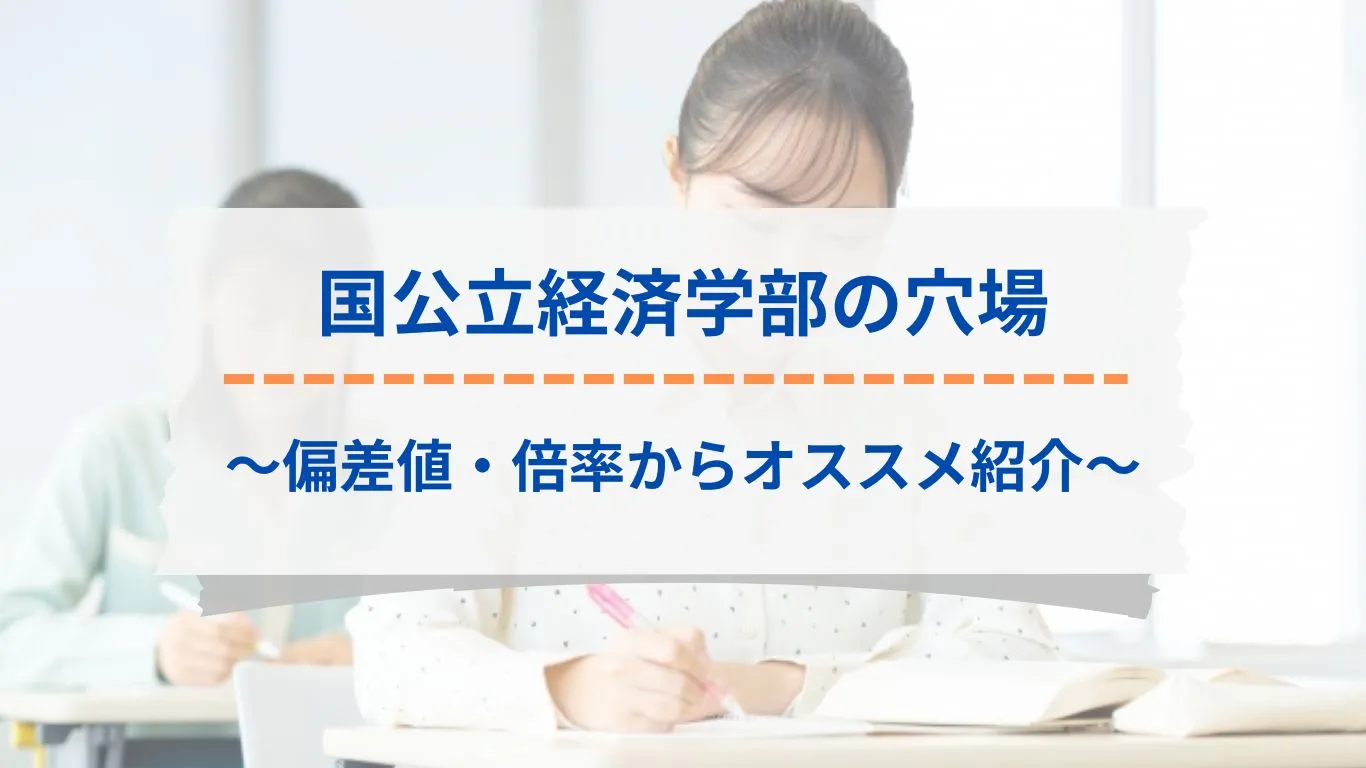
国公立大学の経済学部は、年間授業料が約54万円と私立大学の半額以下で済むうえ、学問的にも実務的にも幅広く学べることから、就職においても金融機関や公務員、一般企業まで多彩な進路を選べる人気の学部です。
特に経済学は景気や政策、国際情勢など、社会の動きを読み解く力を養えるため、安定志向の受験生からも支持を集めています。
そこで本記事では、2025年度入試に対応し、最新の偏差値・倍率データをもとに、難易度が比較的低めでありながら、学びの質や就職実績が充実している“穴場”の国公立経済学部を厳選して紹介します。入試方式や試験科目、立地や学習環境といった受験生にとって重要なポイントも解説するので、「費用を抑えつつ質の高い学びを得たい」「確実に国公立に合格したい」と考えている方はぜひ参考にしてください。
国公立経済学部が“穴場”になる条件
国公立大学の経済学部といっても、全てが高偏差値・高倍率というわけではありません。実は、入試難易度や受験科目の特徴、立地条件によって「意外と狙いやすい大学」が存在します。ここでは、そうした“穴場”と呼べる条件を具体的に整理します。
偏差値が比較的低い
共通テストでの得点率が65〜70%台(偏差値50前後〜55程度)で合格を狙える大学は、全国的に見ても受験のハードルが低めです。特に、首都圏や関西圏から距離がある地方の大学ではこの傾向が顕著で、上位層の受験生が集まりにくい分、合格可能性が高まります。
倍率が低い
倍率が2〜3倍以下で推移している大学は、競争が激化しにくく、比較的安定して合格を狙える環境です。国公立大は受験科目数が多いため、志望者が分散しやすいのですが、それでも人気校は4倍以上になるケースもあるため、低倍率は大きなアドバンテージとなります。
試験科目が少ない/得意科目を活かせる方式がある
一部の大学では、共通テストで5〜6科目必須のところを3〜4科目で受験できる方式や、数学・英語など得意科目の配点比率が高い入試形態を採用しています。受験科目を減らせる大学や、苦手科目の比重を軽くできる大学は、戦略的に「穴場」となります。
地方にあり全国的知名度は低いが、就職実績や教育環境は充実
首都圏や関西の大都市圏から離れた地方大学は、知名度の面で受験生から敬遠されがちですが、地元企業や自治体との結びつきが強く、安定した就職先を確保しているケースも少なくありません。また、学生数が少ない分、教員からのきめ細かな指導やゼミ活動が充実している大学も多く、学びの質はむしろ高い傾向があります。
偏差値・倍率が低めの国公立経済学部一覧
以下は、偏差値・倍率ともに受験しやすく、かつ教育環境が整っている「穴場」国公立経済学部を厳選し、データとともにまとめた一覧表です。志望校選定の参考にどうぞ。
大学一覧
| 大学名 | 偏差値(B判定) | 共通テスト得点率 | 倍率(例年) | 特徴・受験のポイント |
|---|---|---|---|---|
| 高崎経済大学(群馬県) | 50.0〜52.5 | 約69〜74% | 未掲載 | 共テ3教科方式があり科目数少なめなので戦略的受験が可能 |
| 旭川市立大学(北海道) | 不明 | 不明 | 前期:1.8倍(推薦含む) | 地方大学ながら倍率低く、じっくり対策したい人向け |
| 釧路公立大学(北海道) | 不明 | 不明 | 全選抜合計:1.2倍 | 圧倒的に狙いやすい!地方志望なら確保圏 |
| 滋賀大学(滋賀県) | 55.0〜57.5 | 70〜85% | 未掲載 | 滋賀県にあり知名度は高め、実力で勝負しやすい設計 |
| 横浜国立大学(神奈川県) | 62.5〜67.5 | 76〜84% | 未掲載 | 都市圏ながら倍率が高くなく、立地・学力バランス◎ |
各大学のポイント解説
- 高崎経済大学(群馬県)
-
倍率は前期入試で約1.8倍(推薦含む)、募集人数が少ないながらも安定した合格可能性あり。
地元以外の学生には交通コストはあるものの、かなりの穴場です。 - 旭川市立大学(北海道)
-
倍率は前期入試で約1.8倍(推薦含む)、募集人数が少ないながらも安定した合格可能性あり。
地元以外の学生には交通コストはあるものの、かなりの穴場です。 - 釧路公立大学(北海道)
-
全選抜で1.2倍と非常に低倍率。学習時間を確保できているタイプなら安心して合格圏を狙えます。
- 滋賀大学(滋賀県)
-
偏差値55.0〜57.5、共通テストで70〜85%と、国公立としては狙いやすさと学びの質を両立。関西の私立+国公立併願にもおすすめ。
- 横浜国立大学(神奈川県)
-
偏差値62.5〜67.5、共テ76〜84%。都会の国公立としてこの偏差値帯はコスパ良好。都市部で学びたい学生には意外な穴場です。
総評まとめ
- 高崎経済大学・釧路公立大学は、科目数少なめ・低倍率で着実に合格実績を作りたい人に最適。
- 滋賀大学は、自然な範囲の偏差値と教育環境の良さで、コスパ&学びの質の両立を実現。
- 横浜国立大学は、都市圏での進学を希望しつつ、難易度を抑えたい人に狙い目。
偏差値・倍率が低めでも就職に強い国公立経済学部
国公立経済学部の中には、入試難易度が比較的抑えめでも、就職実績や社会的評価が高い大学が存在します。こうした大学は、学費の安さと高い教育水準を両立しており、コストパフォーマンスの面でも非常に優れています。
1. 高崎経済大学(群馬県)
- 就職実績の強み
-
地方自治体や金融業界への就職率が高く、群馬県内の公務員試験合格者数は毎年上位。中小企業との連携や地元企業でのインターンシップ機会も豊富です。
- 穴場ポイント
-
偏差値50前後、共通テスト3科目型で科目負担が少ない。首都圏から新幹線でアクセス可能な立地も魅力。
2. 滋賀大学(滋賀県)
- 就職実績の強み
-
関西圏の大手メーカー、銀行、商社などへの就職率が高く、日経HRの「企業人事が評価する大学ランキング」でも上位常連。少人数ゼミ制度が充実しており、社会人基礎力を伸ばせる環境。
- 穴場ポイント
-
偏差値55〜57.5程度で、関西の国公立の中では狙いやすい。京都・大阪から通学圏内という立地もプラス。
3. 釧路公立大学(北海道)
- 就職実績の強み
-
北海道内の公務員、金融業界への就職が強く、学生数が少ないため教員との距離が近い。就職支援センターによる個別指導が手厚い。
- 穴場ポイント
-
倍率1.2倍と非常に低く、地元志望者以外にとっても受験チャンス大。共通テスト科目数も少なめ。
4. 横浜国立大学(神奈川県)
- 就職実績の強み
-
首都圏企業からの評価が高く、大手総合商社、外資系企業、官公庁への就職者も多い。国際交流プログラムが充実し、海外志向の学生にも適している。
- 穴場ポイント
-
偏差値62.5〜67.5とやや高めだが、都市圏の人気大に比べると倍率は低め。難関私立を目指す層との併願戦略が可能。
穴場の国公立経済学部が就職で強い理由
一見すると入試難易度が抑えめな大学でも、就職活動の場面では大きな強みを発揮する理由があります。これは単なる「偏差値」だけでは測れない要素です。
1. 少人数制でのきめ細かい指導
地方国公立や規模の小さい大学では、ゼミや授業が少人数で行われることが多く、教授と学生の距離が近い環境が整っています。
- 卒業論文や研究指導が手厚く、自己PRで語れる経験が増える
- 公務員試験や資格試験の個別対策を受けやすい
2. 地域企業・自治体との太いパイプ
地方に立地する国公立大学は、地元企業や自治体と強固なネットワークを築いています。
- 学外インターンや地域課題解決型のプロジェクトに参加できる
- Uターン・Iターン就職希望者にとって優位性が高い
3. 国公立ブランドによる信用力
学歴フィルターを持つ企業であっても、国公立という肩書は安定した評価を受けやすい傾向があります。
- 採用担当者からの信頼感が高い
- 学費が安い=経済的に計画性のある学生というイメージを持たれやすい
4. 学費の安さと経済的余裕
国公立大学は年間授業料が約54万円前後と私立に比べて安く、その分、資格取得や留学、インターンなどに資金を回しやすい環境です。こうした経験が就職活動での差別化に直結します。
2025年度入試・偏差値&倍率が低めの国公立経済学部一覧
ここでは、2025年度(令和7年度)入試において偏差値・倍率が全国平均より低めで、かつ就職・教育面の評価が高い経済学部をピックアップしました。
共通テスト得点率・募集人員・倍率などを参考にしており、「狙いやすさ」と「学びの質」を兼ね備えた穴場校を厳選しています。
| 大学名 | 所在地 | 共通テスト得点率(目安) | 一般選抜倍率(前年参考) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 釧路公立大学 | 北海道 | 約68〜70% | 1.9倍 | 北海道東部唯一の公立経済系大学。地域連携やフィールドワークが充実。 |
| 公立諏訪東京理科大学(経営情報学部) | 長野 | 約65〜68% | 2.0倍 | 経済・経営と情報学を融合。地方企業との連携が強い。 |
| 福知山公立大学(地域経営学部) | 京都 | 約66〜69% | 1.8倍 | 公務員志望者の支援が手厚い。地域課題解決型学習が特徴。 |
| 高崎経済大学 | 群馬 | 約69〜71% | 2.3倍 | 首都圏からのアクセス良好。就職率が高く、コスパに優れる。 |
| 名桜大学(国際学部経済系コース) | 沖縄 | 約65〜68% | 1.6倍 | 国際経済や観光経済に強い。留学制度も充実。 |
| 北九州市立大学(経済学部) | 福岡 | 約69〜72% | 2.2倍 | 九州エリア有数の就職実績。OB・OGネットワークが強固。 |
| 岩手県立大学(総合政策学部経済系) | 岩手 | 約67〜69% | 2.0倍 | 政策と経済を学べる。地域貢献型のカリキュラムが多い。 |
選定ポイント
- 偏差値がおおむね65〜70%台で全国平均より低め
- 一般選抜倍率が3倍未満で比較的狙いやすい
- 地方立地による知名度の低さが逆に穴場となっている
- 就職率・資格取得支援・地域連携が充実
穴場の国公立経済学部を攻略するための受験戦略
偏差値や倍率が低めとはいえ、国公立大学の経済学部に合格するには計画的な準備が不可欠です。ここでは、限られた時間で効率よく合格ラインに届くためのポイントを解説します。
出願戦略の立て方
- 科目配点をチェック
- 大学によっては英語や数学の配点が高い場合があります。得意科目が高配点の大学を選ぶことで合格可能性が上がります。
- 共通テストと個別試験のバランス
- 共通テスト重視型(後期試験や共通テスト利用型)を選ぶと、二次試験対策の負担を減らせます。
- 併願パターンの工夫
- 滑り止めには私立の経済・経営系学部を活用し、安心感を持って本命校に挑戦します。
学習の優先順位
- 共通テスト対策を最優先
- 得点率65〜70%台を狙う場合、まずは英語・数学・国語で安定した得点源を確保することが重要です。
- 二次試験科目の早期着手
- 記述力を問われる数学や小論文型試験は、秋以降に一気に伸ばすのは難しいため、夏までに基礎固めを完了。
- 不得意科目の“底上げ”
- 1科目でも極端に低いと合格可能性が大きく下がるため、最低限のラインは早めに突破しておく。
過去問・出題傾向の研究
- 最低3〜5年分は解く
- 出題形式や傾向が毎年似ている大学が多いので、パターンを把握しておくことが有利になります。
- 部分点の取り方を意識
- 記述式では全解答ができなくても、途中式や論理展開をしっかり書くことで得点につながります。
面接・小論文対策(実施校の場合)
- 経済ニュースのインプット
- 日経新聞やNHKニュースなどで経済トピックを押さえ、意見をまとめる練習をしておく。
- 過去の面接質問集の活用
- 「なぜ経済学部なのか」「将来の進路」など定番質問に、自分の経験や関心と絡めて答えられるよう準備。
まとめ|国公立経済学部の穴場はチャンスの宝庫
国公立大学の経済学部は、学費の安さ・就職の強さ・学びの幅広さという三拍子がそろった人気学部です。その中でも偏差値や倍率が低めの“穴場校”は、受験戦略の中で大きな武器になります。
難関校だけを視野に入れると、どうしても合格ラインが高くなり、浪人や併願校の負担が増えがちです。しかし、倍率や偏差値が抑えめの大学をうまく組み合わせれば、合格可能性を広げつつ、将来の選択肢も確保できます。
また、地方の国公立経済学部は、地域経済や産業と密接に結びついた実践的な学びや、少人数ゼミを通じた手厚い指導が魅力。知名度が高くなくても、就職や資格取得で強みを発揮できる大学は少なくありません。
入試科目の特徴や配点バランス、過去の倍率推移などをよく分析し、自分の得意科目を活かせる大学を選ぶことが合格への近道です。2025年度入試の最新データを参考に、自分に合った“チャンスの宝庫”を見つけてください。